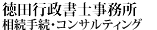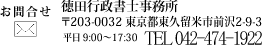遺 言
遺言は、自分が生涯をかけて築いた大切な財産を、有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。遺言がないために、相続をめぐり親族間で争いが生じることが多々あります。遺言はそのような争いを防止するため、遺言者自らが自分の残した財産の帰属を決める制度です。
遺言がない場合
遺遺言のない場合は、民法が相続人の相続分を定めていますので、民法に従って遺産を分けることになります(これを「法定相続」といいます。)。
遺言の効用
民法は相続分の割合を一律に定めているだけなので、遺産の帰属を具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割の協議を行って決める必要がありますが、自主的に協議をまとめるのは、必ずしも容易なことではありません。遺言で相続財産を具体的に決めておけば、争いを未然に防ぐことができます。
遺言の必要性が特に強い場合
① 夫婦の間に子供がいない場合
夫婦の間に子供がいない場合、法定相続となると、夫の財産は、夫の両親がすでに亡くなっている場合、妻が4分の3、夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。しかし、長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う方も多いと思います。そして、それを可能にするためには、遺言をしておくことが必要になります。兄弟には、遺留分がありませんから、遺言さえしておけば、財産をすべて妻に残すことができます。
② 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻との間では遺産争いが起こる確率も非常に高いので、争いの発生を未然に防ぐため、遺言できちんと定めておく必要性が特に強いと言えるでしょう。
③ 長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
長男死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には、その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが、嫁は相続人ではないので、遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておかないと、お嫁さんは何ももらえないことになってしまいます。
④ 内縁の妻の場合
長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届けを出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、内縁の妻に相続権がありません。したがって、内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言をしておかなければなりません。
⑤
個人で事業を経営したり、農業をしている場合
その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が困難になる場合があります。このような事態を招くことを避け、家業等を特定の者に承継させたい場合には、その旨きちんと遺言をしておかなければなりません。
⑥
各相続人毎に承継させたい財産を指定したい場合
例えば、不動産はお金や預貯金と違い、事実上皆で分けることが困難な場合が多いでしょうから、これを誰に相続させるか決めておくとよいでしょう。あるいは、身体障害のある子に多くあげたいとか、遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたいとか、孫に遺贈したいとかのように、遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、妥当性のある形で財産承継をさせたい場合には、遺言をしておく必要があります。
⑦ 相続人が全くいない場合
相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。したがって、このような場合に、特別世話になった人に遺贈したいとか、お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体、あるいは、ご自分が有意義と感じる各種の研究機関等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。
遺言の種類
遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言はすべて無効です。
遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という、3つの方式が定められています。
①自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文(目録を含むすべて)を手書きし、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です(すべてを自書しないとだめで、パソコンやタイプライターによるものは無効です。ただし,令和1年1月13日から,民法改正によりパソコン等で作成した目録を添付したり,銀行通帳のコピーや不動産登記事項証明書等を目録として添付することが認められるようになりました。)。
自筆証書遺言は、自分で書けばよいので、費用もかからず、いつでも書けるというメリットがあります。
デメリットとしては、内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合には、法律的に見て不備な内容になってしまう危険があり、後に紛争の種を残したり、無効になってしまう場合もあります。しかも、誤りを訂正した場合には、訂正した箇所に押印をし、さらに、どこをどのように訂正したかということを付記して、そこにも署名しなければならないなど方式が厳格なので、方式不備で無効になってしまう危険もつきまといます。
また、自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、必ず家庭裁判所にこれを持参し、その遺言書を検認するための手続を経なければなりません。
さらに、自筆証書遺言は、これを発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには、破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえません。
また、自筆証書遺言は全文自書しないといけないので、当然のことながら、病気等で手が不自由になり、字が書けなくなった方は、利用することができません。
②公正証書遺言
自筆証書遺言のもつ様々なデメリットを補う遺言の方式として、公正証書遺言があります。
公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、公証人がそれに基づいて遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
遺言者が遺言をする際には、どんな内容の遺言にしようかと思い悩むことも少なくないと思いますが、そんなときも公証人が相談を受けながら、必要な助言をしたりして、遺言者にとって最善と思われる遺言書を作成していくことになります。
公証人は、多年、裁判官、検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で、正確な法律知識と豊富な経験を有していますので、複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にしますし、もとより方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。
また、公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
また、自筆証書遺言は、全文自分で自書しなければなりませんので、体力が弱ってきたり、病気等のため自書が困難となった場合には、自筆証書遺言をすることはできませんが、公証人に依頼すれば、このような場合でも、遺言をすることができます。署名することさえできなくなった場合でも、公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められています。
なお、遺言者が高齢で体力が弱り、あるいは病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
③秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり、自書である必要はないので、ワープロ等を用いても、第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で、これを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人がその封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。
上記の手続を経由することにより、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき、かつ、遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができますが、公証人はその遺言書の内容を確認することはできませんので、遺言書の内容に法律的な不備があったり、紛争の種になったり、無効となってしまう危険性がないとはいえません。
また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように、この遺言書を発見した者が、家庭裁判所に届け出て、検認手続を受けなければなりません。
遺言はいつ行うか
遺言は、死期が近づいてからするものと思っている方がいますが、それは全くの誤解です。人間はいつ何時、何があるかも分かりません。いつ何があっても、残された家族が困らないように配慮してあげるのが、遺言の作成ということなのです。つまり遺言は、自分が元気なうちに、愛する家族のために、自分に万一のことがあっても残された者が困らないように作成しておくべきものなのです。ちなみに最近では、かなり若い人でも、海外旅行へ行く前等に遺言書を作成する例も増えています。遺言は、後に残される家族に対する最大の思いやりなのです。
遺言は、判断能力があるうちは、死期が近くなってもできますが、判断能力がなくなってしまえば、もう遺言はできません。遺言をしないうちに判断能力がなくなったり、死んでしまっては後の祭りで、そのために家族の悲しみが倍加する場合もあることでしょう。つまり遺言は、元気なうちに、備えとして、これをしておくべきものなのです。ちなみに遺言は、満15歳以上になれば、いつでもできます。
遺言の訂正、取消し(撤回)
遺言は、人の最終意思を保護しようという制度ですから、訂正や取消し(遺言の取消しのことを、法律上は「撤回」と言います。)は、いつでも、また、何回でもできます。遺言は、作成したときには、それが最善と思って作成した場合でも、その後の家族関係を取り巻く諸状況の変化に応じ、あるいは心境が変わったり、考えが変わったりして、訂正したり、撤回したいと思うようになることもあると思います。さらに、財産の内容が大きく変わった場合にも、多くの場合、書き直した方がよいといえるでしょう。
遺言は、遺言作成後の諸状況の変化に応じて、いつでも自由に、訂正や撤回することができます。ただ、訂正や撤回も、遺言(その種類は問いません。)の方式に従って、適式になされなければなりません。
負担付遺贈
年老いた親にとって、障害を抱えた子の将来ほど心配なことはないでしょう。もし、誰かその子の面倒を見てくれるという信頼できる人や機関が見つかれば、その子の面倒を見てもらう代わりに、その人や機関に、それにふさわしい財産を遺贈したいと思われるのも、ごく自然なことと思います。民法は、このように、財産の遺贈を受ける人(「受遺者」と言います。)に一定の負担を与える遺贈のことを、「負担付遺贈」として、規定を置いています(民法1002条)。
また、負担付遺贈とは別に、遺言によって財産を信頼できる人や機関に財産を譲渡するなどし、その人や機関に障害を持つ子のために財産を管理・処分し必要なことを行ってもらう「遺言信託」(信託法3条2号)という制度もあります。いずれにしろ、このような遺言をする場合には、受遺者となるべき人又は機関と、事前に十分話し合っておくことが必要と思われます。
予備的遺言
相続人や受遺者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合(以前とは、遺言者より先に死亡した場合だけでなく、遺言者と同時に死亡した場合も含みます。)、遺言の当該部分は失効してしまいます。したがって、そのような心配のあるときは、予備的に、例えば、「もし、妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を、誰々に相続させる。」と決めておけばよいわけです。これを「予備的遺言」といいます。